
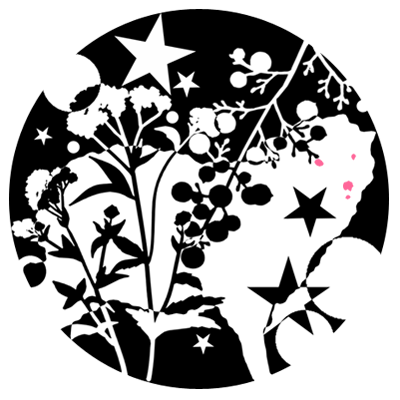
花弁に埋もるる
それは、天気の良い昼間のことだった。
フェラーリンはちょうど建物の中の廊下を歩いており、窓の外にふと目をやると軍のロゴマークが入ったつなぎを来た人影が飛行艇の傍に居るところを目にした。つなぎを着ているのは整備士で、明るい茶色をしたふわふわの髪の毛が飛行艇の影からひょっこりと見える。顔や姿全体は飛行艇の影に隠れていてよく見えないが、誰だかはすぐに分かってフェラーリンは窓に向き合って少し動きを見ていた。
整備士のすることと言ったら整備しかないから、特に大きな出来事も無いはずが頭が機体の傍にとさりと転がる光景を目にした。
「!?」
フェラーリンはぎょっとして目を見張る。
細い腕と、髪の毛が無造作に地面に投げ出されており、一瞬で倒れたのだと理解した。
咄嗟に窓を開けて思い当たる名前を叫んだ。
「!」
そのままフェラーリンは一階に居たのを良いことに窓に足をかけ外に飛び出して駆け寄った。近づいてみるとやはりフェラーリンの予想は正しく、がぐったりと地面に伏していた。
「おい、しっかりしろ、大丈夫か!?」
薄い肩を掴み顔を見てみると血色が悪くまるで眠っているように静かに目を瞑っていた。
呼吸は正常だが脈拍は少し弱く、フェラーリンは眉をしかめる。
の肩を抱き上げ、膝の後ろに腕を差込み抱き上げると、あまりの軽さに一瞬戸惑った。
「え、あれ?!?」
「どうしたんですっ?」
足早に建物の中に入ると何人かの隊員に会い少し驚かれる。
「外で倒れていたのを見つけた……医務室に連れて行く」
「俺、大尉たちに声かけてきます!」
バタバタと走って行く若い隊員に頼むと声をかけてから、フェラーリンは廊下を足早に歩いた。途中何人かとすれ違いその都度驚かれるが口を開いている余裕も無く、の細い身体を力強く抱きしめる。
医務室のベッドに寝かせると、マルコたちの幼馴染みという名の保護者が続々と駆け込んで来た。フェラーリンは彼らにを任せた。
暫くして、休憩所でコーヒーを飲みながら海と空を眺めていたフェラーリンの元へ、マルコがやってきた。
「ようフェラーリン」
「……容態は?」
煙草に火をつけたマルコはフェラーリンの隣に立ち、同じように空と海が広がる景色を眺める。
「大丈夫なのか?あんなに真っ青な顔をしていたが」
「いつものことだ……なんて言いたくはねえが、本当によくあることなんだ」
困ったものだと、マルコが白い煙をゆっくりと吐き出して憂鬱な表情を浮かべた。
「身体が弱いのか?」
「そう言うわけじゃねえんだが、昔から小食でな……しかもすぐに食事を忘れちまう」
が軍に入ってきて二年、会ってから半年以上のときが流れたが、倒れるという事態は初めてだ。
「忘れる?いくらなんでもそれは、酷すぎるぞ……大丈夫なのか?」
「大丈夫じゃねえよ、現にこうして倒れてる……」
ここ一年倒れるほどまではいかないようになっていたのだが、とマルコは呟いた。フェラーリンはまるで今まではしょっちゅう倒れていたという口ぶりに驚愕を禁じえない。思わず今までどういう生活を送っていたのかと聞きたくなった。
「昔より倒れる回数は減ったが、悪化してる」
「どういうことだ」
「飯を食うのを忘れるだけじゃねえ……咽を通らなくなっちまってんだ」
「……、通らなく?」
「本人は何にも言わねえがな……」
煙草の火を消したマルコから部屋を出る間際に、運んでくれてありがとよ……と言われたが、フェラーリンは言葉を返せなかった。
医務室でマルコやベルリーニを初めとするたくさんの人々に心配され、怒られ、たしなめられ、は空軍の末っ子と呼ばれるほどになってしまった。
マルコを筆頭とする昔馴染みに構われていたが、細すぎる身体は軍の男達にしてみたら今にも死に掛けている小動物のようで、それ以外にもやたら可愛がられていたらしい。フェラーリンもそこそこ目をかけてはいたがの人気を知らなかった為、医務室に来た数だけある見舞い品の果物やパンや菓子の量に、フェラーリンは目を見開いた。
「凄い量だな……」
ジーナにベルリーニが電話で報告した際、暫く安静にして医務室で見舞いの品を消費しなさいと言われ、はうんざりしながら、あまり腹にたまらなそうな食品を選びちびちび食べていた。
様子を見にやってきたフェラーリンは見舞い品の数々を見渡しながらぼそりと呟く。
「あ、フェラーリンさん……こんにちは」
「よう、末っ子。見舞いの品持ってきたぞ」
「え、や、やめてくださいよこれ以上―――」
「チョコレートは好きか?」
これ以上食べられませんといいかけたは持っていたサンドウィッチのレタスがはみ出るくらい手に力を込めた。
末っ子という単語も見舞いの品も色々言いたいことがあるがフェラーリンはさくさくと話を進めていくため、口を挟めない。
「へ、チョコ……ですか?」
リンゴやオレンジ、パンケーキにチーズ、仕舞には肉というボリューミーなものばかり食べさせられていたはきょとりと首を傾げた。チョコレートくらいなら食べられるし、甘いものは頭を働かせるにはもってこいだから嫌いではない。
「造血にもなるし、このくらいの量なら食べられるだろう」
「あ、……」
ぽん、とベッドの上に置かれたのは小さな籠に入った、コインの形をしたチョコレートだ。
「食事が咽を通らない時でも、このくらい食べておけ」
ぽすりと頭を撫でられ、は涙が零れそうになるのを我慢した。フェラーリンは、のしてほしいことを一瞬でやってのけてしまう。それも、単純にそれとなく。
食べようと思っても咽を通らなくて食事を抜くこともあるにとってはこのくらい小さくて、口の中に入れれば解けてしまうチョコレートは正直助かる。
「ありがとうございます、フェラーリンさん」
「ああ」
「チョコレート、好きです」
にとってチョコレートは嫌いではないという認識だったが、今回のことで好きになりそうだった。
「そうだ、あの、自分を見つけてくれたのも運んでくれたのもフェラーリンさんだと伺いました」
「ああ、窓の外を見ていたら、急に倒れるから吃驚した」
「ご迷惑をおかけしました……あと、ありがとうございました」
迷惑じゃなくて心配だ、との言葉を訂正してからフェラーリンは笑った。
「お前が倒れたらすぐに連れ出してやる」
も安心したような顔つきで頬を緩めたが、次に続くフェラーリンの言葉にぴしりと固まった。
「…………そうしたら空軍の末っ子ではなく空軍のお姫様と呼ばれるようになるだろうな」
主人公は愛されてるというよりも心配されてる。
フェラーリンはちょうど建物の中の廊下を歩いており、窓の外にふと目をやると軍のロゴマークが入ったつなぎを来た人影が飛行艇の傍に居るところを目にした。つなぎを着ているのは整備士で、明るい茶色をしたふわふわの髪の毛が飛行艇の影からひょっこりと見える。顔や姿全体は飛行艇の影に隠れていてよく見えないが、誰だかはすぐに分かってフェラーリンは窓に向き合って少し動きを見ていた。
整備士のすることと言ったら整備しかないから、特に大きな出来事も無いはずが頭が機体の傍にとさりと転がる光景を目にした。
「!?」
フェラーリンはぎょっとして目を見張る。
細い腕と、髪の毛が無造作に地面に投げ出されており、一瞬で倒れたのだと理解した。
咄嗟に窓を開けて思い当たる名前を叫んだ。
「!」
そのままフェラーリンは一階に居たのを良いことに窓に足をかけ外に飛び出して駆け寄った。近づいてみるとやはりフェラーリンの予想は正しく、がぐったりと地面に伏していた。
「おい、しっかりしろ、大丈夫か!?」
薄い肩を掴み顔を見てみると血色が悪くまるで眠っているように静かに目を瞑っていた。
呼吸は正常だが脈拍は少し弱く、フェラーリンは眉をしかめる。
の肩を抱き上げ、膝の後ろに腕を差込み抱き上げると、あまりの軽さに一瞬戸惑った。
「え、あれ?!?」
「どうしたんですっ?」
足早に建物の中に入ると何人かの隊員に会い少し驚かれる。
「外で倒れていたのを見つけた……医務室に連れて行く」
「俺、大尉たちに声かけてきます!」
バタバタと走って行く若い隊員に頼むと声をかけてから、フェラーリンは廊下を足早に歩いた。途中何人かとすれ違いその都度驚かれるが口を開いている余裕も無く、の細い身体を力強く抱きしめる。
医務室のベッドに寝かせると、マルコたちの幼馴染みという名の保護者が続々と駆け込んで来た。フェラーリンは彼らにを任せた。
暫くして、休憩所でコーヒーを飲みながら海と空を眺めていたフェラーリンの元へ、マルコがやってきた。
「ようフェラーリン」
「……容態は?」
煙草に火をつけたマルコはフェラーリンの隣に立ち、同じように空と海が広がる景色を眺める。
「大丈夫なのか?あんなに真っ青な顔をしていたが」
「いつものことだ……なんて言いたくはねえが、本当によくあることなんだ」
困ったものだと、マルコが白い煙をゆっくりと吐き出して憂鬱な表情を浮かべた。
「身体が弱いのか?」
「そう言うわけじゃねえんだが、昔から小食でな……しかもすぐに食事を忘れちまう」
が軍に入ってきて二年、会ってから半年以上のときが流れたが、倒れるという事態は初めてだ。
「忘れる?いくらなんでもそれは、酷すぎるぞ……大丈夫なのか?」
「大丈夫じゃねえよ、現にこうして倒れてる……」
ここ一年倒れるほどまではいかないようになっていたのだが、とマルコは呟いた。フェラーリンはまるで今まではしょっちゅう倒れていたという口ぶりに驚愕を禁じえない。思わず今までどういう生活を送っていたのかと聞きたくなった。
「昔より倒れる回数は減ったが、悪化してる」
「どういうことだ」
「飯を食うのを忘れるだけじゃねえ……咽を通らなくなっちまってんだ」
「……、通らなく?」
「本人は何にも言わねえがな……」
煙草の火を消したマルコから部屋を出る間際に、運んでくれてありがとよ……と言われたが、フェラーリンは言葉を返せなかった。
医務室でマルコやベルリーニを初めとするたくさんの人々に心配され、怒られ、たしなめられ、は空軍の末っ子と呼ばれるほどになってしまった。
マルコを筆頭とする昔馴染みに構われていたが、細すぎる身体は軍の男達にしてみたら今にも死に掛けている小動物のようで、それ以外にもやたら可愛がられていたらしい。フェラーリンもそこそこ目をかけてはいたがの人気を知らなかった為、医務室に来た数だけある見舞い品の果物やパンや菓子の量に、フェラーリンは目を見開いた。
「凄い量だな……」
ジーナにベルリーニが電話で報告した際、暫く安静にして医務室で見舞いの品を消費しなさいと言われ、はうんざりしながら、あまり腹にたまらなそうな食品を選びちびちび食べていた。
様子を見にやってきたフェラーリンは見舞い品の数々を見渡しながらぼそりと呟く。
「あ、フェラーリンさん……こんにちは」
「よう、末っ子。見舞いの品持ってきたぞ」
「え、や、やめてくださいよこれ以上―――」
「チョコレートは好きか?」
これ以上食べられませんといいかけたは持っていたサンドウィッチのレタスがはみ出るくらい手に力を込めた。
末っ子という単語も見舞いの品も色々言いたいことがあるがフェラーリンはさくさくと話を進めていくため、口を挟めない。
「へ、チョコ……ですか?」
リンゴやオレンジ、パンケーキにチーズ、仕舞には肉というボリューミーなものばかり食べさせられていたはきょとりと首を傾げた。チョコレートくらいなら食べられるし、甘いものは頭を働かせるにはもってこいだから嫌いではない。
「造血にもなるし、このくらいの量なら食べられるだろう」
「あ、……」
ぽん、とベッドの上に置かれたのは小さな籠に入った、コインの形をしたチョコレートだ。
「食事が咽を通らない時でも、このくらい食べておけ」
ぽすりと頭を撫でられ、は涙が零れそうになるのを我慢した。フェラーリンは、のしてほしいことを一瞬でやってのけてしまう。それも、単純にそれとなく。
食べようと思っても咽を通らなくて食事を抜くこともあるにとってはこのくらい小さくて、口の中に入れれば解けてしまうチョコレートは正直助かる。
「ありがとうございます、フェラーリンさん」
「ああ」
「チョコレート、好きです」
にとってチョコレートは嫌いではないという認識だったが、今回のことで好きになりそうだった。
「そうだ、あの、自分を見つけてくれたのも運んでくれたのもフェラーリンさんだと伺いました」
「ああ、窓の外を見ていたら、急に倒れるから吃驚した」
「ご迷惑をおかけしました……あと、ありがとうございました」
迷惑じゃなくて心配だ、との言葉を訂正してからフェラーリンは笑った。
「お前が倒れたらすぐに連れ出してやる」
も安心したような顔つきで頬を緩めたが、次に続くフェラーリンの言葉にぴしりと固まった。
「…………そうしたら空軍の末っ子ではなく空軍のお姫様と呼ばれるようになるだろうな」
主人公は愛されてるというよりも心配されてる。
やせ細った動物感覚で
2012/04/11
![]()
![]()
![]()
Title
by
yaku 30
no uso