
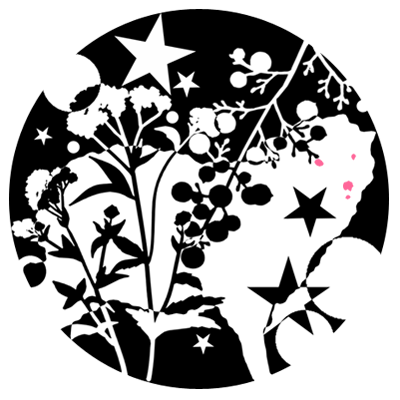
もっと上手に見つめていて
マルコから軍を辞めると言われた時、本当はもついて行くつもりでいた。
けれどどうしてだか断っていて、彼を見送る時に自分の人生もここで終わりなのかもしれないと思った。
幼馴染み達はにとっては皆同じくらい大事だけど、一番影響力のあるマルコの居ない軍で生きて行ける気がしないのだ。
その夜はやはりあまり寝付けないけれど、数時間くらいは眠れるのでいつもと変わらなかった。
朝の気怠さもいつもと同じで、マルコが居なくても生きていた。当然のことなのだが。
朝食は相変わらず腹に入れずチョコレートをひとかけら食べて水を飲んで身支度を整える。足取りの重さもおそらくいつもと変わらない。
エドモンドとマルコはもういないのかと二人で会話をしても、たとえば急に心臓が止まるとか、マルコの居ない寂しさで泣き出すとか、そんなこともなかった。
「なんだろう……」
数日間、マルコの居ない軍でも普通に過ごしてしまった。
彼が豚になったと聞いて、エドモンドは会いに行こうぜと笑っていた。もちょっと会いたいと思った。
胸を撫でて、心臓が動いているのを確認して、首を傾げる。
「具合が悪いのか?」
休憩のため、倉庫の外でぽつりと立っていたの様を見て近寄って来たのはフェラーリンだ。
心配そうに、見るからに不健康なの顔を覗き込む。
具合が悪いのは慢性的なことなのだけど、とは口にはせず、胸に手を当てたままドクンドクンと荒立てる心臓の音を掌で感じた。
ぽかんとしてフェラーリンの顔を見返してしまう。
「いえ、いい具合です」
「おかしな答えだな」
ふっと笑ったフェラーリンはくしゃりと頭を撫でて来た。緩いつなぎの胸の部分をぎゅっと抑え、受け入れるように顎を引いて目を瞑る。つられて笑うは胸も首も頬もぽかぽかと温かくなるのを感じた。そしていつかマルコが言っていた言葉も理解した。
彼の手が離れて行くのが惜しい。指先を見送るのは、マルコの背と同じくらい切なかった。それがどういうことなのかはもう知っている。
無意識に首を振り断ったのも、チョコレートが好きなのも、支えが喪われて行くこの場所に居るのは、大きな支柱があったから。マルコが自分を作ってくれたというのなら、フェラーリンは自分を生かしてくれる。
だから一番好きな人と一緒に居るのが良いとマルコは言うのだろう。
「もう少し、撫でてください」
「―――ああ」
マルコを引き止めることはできなかったけれど、フェラーリンの手は引き止められた。
口に出した途端に恥ずかしくなるが、もう一度頭を撫でられたので顔を隠す機会は得られる。くふくふと笑うを見て、フェラーリンはきっと深い意味など感じないだろう。
「マルコが居なくて寂しいか」
「いいえ」
こんな風に勘違いをして、ため息まじりに撫で続けてくれるその手は、動きが少し緩くなった。
ほっとしながら顔を上げて、フェラーリンの困った顔を見る。本当に、寂しくないのだ、は。
「マルコは生きていますから」
今度はが苦笑する番だった。
勘違いをしてくれたのは助かるが、さすがにそんな甘えん坊の子供ではないと言いたい。
けれどやっぱり、撫でてもらう理由にする為には少しだけ寂しいふりをしていた方が良いのかもしれない。
フェラーリンは柔らかい髪の毛を撫でて、地肌に指を滑らせる。
の幼馴染みが死んでから、酷いものだった。あのマルコでさえ嫌気がさして軍から出て行って、しまいには自分から魔法をかけて豚までなっているというのに、この痩せっぽちの青年は、さらに痩せっぽちになっていくだけだ。どちらが酷いのかわからないが、の方が可哀相でしかたがない。
青白い顔も、隈の浮かぶ目元も、細い首も、すべてどうにかしてやりたい。
けれどそんな方法はわからず、どうにかならないものかと他力本願な事を考えていた。
唯一残った馴染みのエドモンドも、を心配しているのだがが健康的になる兆しは一向にない。マルコや、エドモンド、ジーナでさえ無理ならばフェラーリンにはどうすることもできないのだろう。
「ちゃんと眠っていないんだろう」
「はい……」
見るからに眠っていなさそうな顔をしているが、月並みな説教をしてしまった。
けれどは叱られたという顔をしないし、むしろ笑う。こちらとしては身を案じているのだが、どうにも伝わらない。
「どうにかならないか、その不健康な暮らしは」
「こればかりは、どうにも」
もう少し時間が欲しいと、小さく呟いたは作業に戻ると敬礼してフェラーリンから離れて行った。
細く薄い肩を抱き寄せて捕まえて、この腕に閉じ込め、甘やかしたら彼が幸福になれるというならば、今すぐにそうするのに。けれどそうはならないだろうと思い、拳を握り自身もその場から離れた。
主人公もっと子供っぽいんだけど、フェラーリンさん上官(っていうの?)なので割と年相応になりますね。あと主人公のストレスがあれだから。
けれどどうしてだか断っていて、彼を見送る時に自分の人生もここで終わりなのかもしれないと思った。
幼馴染み達はにとっては皆同じくらい大事だけど、一番影響力のあるマルコの居ない軍で生きて行ける気がしないのだ。
その夜はやはりあまり寝付けないけれど、数時間くらいは眠れるのでいつもと変わらなかった。
朝の気怠さもいつもと同じで、マルコが居なくても生きていた。当然のことなのだが。
朝食は相変わらず腹に入れずチョコレートをひとかけら食べて水を飲んで身支度を整える。足取りの重さもおそらくいつもと変わらない。
エドモンドとマルコはもういないのかと二人で会話をしても、たとえば急に心臓が止まるとか、マルコの居ない寂しさで泣き出すとか、そんなこともなかった。
「なんだろう……」
数日間、マルコの居ない軍でも普通に過ごしてしまった。
彼が豚になったと聞いて、エドモンドは会いに行こうぜと笑っていた。もちょっと会いたいと思った。
胸を撫でて、心臓が動いているのを確認して、首を傾げる。
「具合が悪いのか?」
休憩のため、倉庫の外でぽつりと立っていたの様を見て近寄って来たのはフェラーリンだ。
心配そうに、見るからに不健康なの顔を覗き込む。
具合が悪いのは慢性的なことなのだけど、とは口にはせず、胸に手を当てたままドクンドクンと荒立てる心臓の音を掌で感じた。
ぽかんとしてフェラーリンの顔を見返してしまう。
「いえ、いい具合です」
「おかしな答えだな」
ふっと笑ったフェラーリンはくしゃりと頭を撫でて来た。緩いつなぎの胸の部分をぎゅっと抑え、受け入れるように顎を引いて目を瞑る。つられて笑うは胸も首も頬もぽかぽかと温かくなるのを感じた。そしていつかマルコが言っていた言葉も理解した。
彼の手が離れて行くのが惜しい。指先を見送るのは、マルコの背と同じくらい切なかった。それがどういうことなのかはもう知っている。
無意識に首を振り断ったのも、チョコレートが好きなのも、支えが喪われて行くこの場所に居るのは、大きな支柱があったから。マルコが自分を作ってくれたというのなら、フェラーリンは自分を生かしてくれる。
だから一番好きな人と一緒に居るのが良いとマルコは言うのだろう。
「もう少し、撫でてください」
「―――ああ」
マルコを引き止めることはできなかったけれど、フェラーリンの手は引き止められた。
口に出した途端に恥ずかしくなるが、もう一度頭を撫でられたので顔を隠す機会は得られる。くふくふと笑うを見て、フェラーリンはきっと深い意味など感じないだろう。
「マルコが居なくて寂しいか」
「いいえ」
こんな風に勘違いをして、ため息まじりに撫で続けてくれるその手は、動きが少し緩くなった。
ほっとしながら顔を上げて、フェラーリンの困った顔を見る。本当に、寂しくないのだ、は。
「マルコは生きていますから」
今度はが苦笑する番だった。
勘違いをしてくれたのは助かるが、さすがにそんな甘えん坊の子供ではないと言いたい。
けれどやっぱり、撫でてもらう理由にする為には少しだけ寂しいふりをしていた方が良いのかもしれない。
フェラーリンは柔らかい髪の毛を撫でて、地肌に指を滑らせる。
の幼馴染みが死んでから、酷いものだった。あのマルコでさえ嫌気がさして軍から出て行って、しまいには自分から魔法をかけて豚までなっているというのに、この痩せっぽちの青年は、さらに痩せっぽちになっていくだけだ。どちらが酷いのかわからないが、の方が可哀相でしかたがない。
青白い顔も、隈の浮かぶ目元も、細い首も、すべてどうにかしてやりたい。
けれどそんな方法はわからず、どうにかならないものかと他力本願な事を考えていた。
唯一残った馴染みのエドモンドも、を心配しているのだがが健康的になる兆しは一向にない。マルコや、エドモンド、ジーナでさえ無理ならばフェラーリンにはどうすることもできないのだろう。
「ちゃんと眠っていないんだろう」
「はい……」
見るからに眠っていなさそうな顔をしているが、月並みな説教をしてしまった。
けれどは叱られたという顔をしないし、むしろ笑う。こちらとしては身を案じているのだが、どうにも伝わらない。
「どうにかならないか、その不健康な暮らしは」
「こればかりは、どうにも」
もう少し時間が欲しいと、小さく呟いたは作業に戻ると敬礼してフェラーリンから離れて行った。
細く薄い肩を抱き寄せて捕まえて、この腕に閉じ込め、甘やかしたら彼が幸福になれるというならば、今すぐにそうするのに。けれどそうはならないだろうと思い、拳を握り自身もその場から離れた。
主人公もっと子供っぽいんだけど、フェラーリンさん上官(っていうの?)なので割と年相応になりますね。あと主人公のストレスがあれだから。
マルコが豚になったのはある意味吹っ切れてることって気もするので、酷いとは言わないかもですね。
2016/04/15
![]()
![]()
![]()
Title
by
yaku 30
no uso