
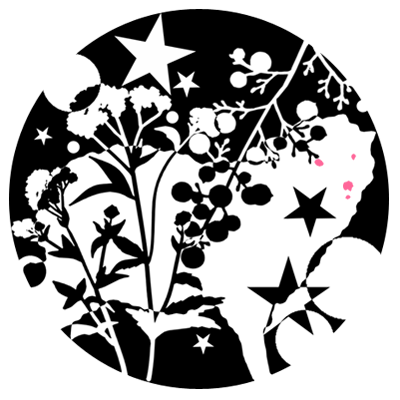
砂糖見ず
「なぜ、マルコと共に行かなかった」
世界から拒絶されたような気がした。
ぎこちなく笑うだが、今にも泣きだしてしまいそうな顔をしている。
ただでさえ憔悴していたのに、この言葉はとても堪えた。
仲間を戦場や訓練に送り出す度、食事が喉を通らなくなりそうだったがチョコレートを口に含んでなんとか脳や胃を刺激して、寝付けない夜でも疲れて眠り落ちるまでじっと耐えた。
明日はフェラーリンに会える。
彼の飛行艇を整備しよう。
おはよう、と言ってもらえたらいい。
こんな風に希望を胸に抱いて眠る為には、フェラーリンの存在が必要不可欠だった。
軍を裏切ることはできない、とは思っていない。たとえば、マルコではなくフェラーリンが退役するのなら、迷わず自分も軍の整備士を辞めてジーナの店の手伝いをしながら、時折フェラーリンがやってきてくれないかとピアノを弾きながら待つだろう。
だから充分、自分の欲望に忠実に生きている。
心配されても、追い出されたくはなかった。
「もし……俺が帰って来なかったらどうする」
フェラーリンの悲しそうな顔を見て、昂りがすっと冷めて行く。
けれど溢れ出た涙が目の奥に戻るわけがなく、眼窩に溜まる水分は今にも零れそうに揺れていた。
それはずっと考えていたことだった。否、考える必要もなかった。
「―――眠るよ」
彼が帰らぬ人となったら、酷く傷つき、起きてすらいられないだろう。
瞬きと同時に涙が落ちて鎖骨に跳ねた。
「二度と目を覚ますことがないように」
なにも、怖いことなどない。
フェラーリンは目を見開いて、肩を掴む手を少し緩める。けれどそれは離れて行かず、首と顎を伝って耳の下や後ろを撫でた。心地良いと思いながら、近づいて来る顔を眺めて目を瞑る。
呼吸を止めるのはほんの数秒でよかった。
音もなく触れ合った唇は、離れたと同時に熱い息を零す。薄目で彼の開いた口を眺めて、顔をすり寄せてもう一度と強請ると、息を飲み込むような音を立てて再び口を塞がれた。
廊下ですることではないと互いに思っていたので、自然と体は動いて廊下の影に潜む。
放さないとばかりに後頭部と腰を押さえる手も、甘えるように首筋と米神をくすぐる手も、触れているところの全てが熱い。
「……」
呼吸のついでに愛称を呼ばれると照れくさくて、唇を啄み返事の代わりにする。
今度はが名前を呼ぼうとすれば、声にする前に飲み込まれた。
程なくして、人の足音や気配がしたので離れて、襟や髪を整え、言葉もなく二人は別れた。
は家に帰って、フェラーリンの言葉を反芻して涙を零した。エドモンドが死んだと受け止めたときよりも、長く長く。
キスよりも言われた言葉の方が重たい。
どちらも、嘘ではないのだ。フェラーリンはを思って言ってくれて、してくれた。
彼の気持ちも分かる。けれど。
一晩泣いて、次の日にははこっそりと辞表を出し、荷物をまとめて部屋を出ていった。
誰にも会わず、半ば逃げるように姿を消したが辞表を見た者はおそらく納得し、追いかけてくることはないだろう。
マルコのように、賞金稼ぎなんかをしていなければ。
はまずジーナの店に行った。軍を辞めたと言うと、彼女はそれ以上聞かずにに一室用意して、一週間近くバカンスのようなのんびりとした生活を提供してくれた。料金は支払うと最初言ったのだが、店で演奏してくれれば良いと言われたのではあっさりと頷いた。店内ではずっと演奏し続けていれば挨拶にまわることもなく、ただ没頭できる。ピアノを弾いているところを邪魔をして来る客はジーナの店にはいない。
軍の関係者が店に顔を出す事は稀だったが、数人は来るものでの姿を見ると少し驚いたようだった。けれど誰も演奏を中断させることなく帰って行った。
数日するとフェラーリンが顔を出したが、は無視してピアノを引き続けた。
それは、彼がそう望んだことだ。こうして、のんびりピアノを弾いている生活を送ってほしいと思っているのだろう。そう言いたげに、は視線を一向にやらなかった。やはりフェラーリンは声をかけずに帰って行き、それでも週に一度くらいの頻度でやって来た。
「なんか、もう、鬱陶しい」
「なあに?急にふてくされて」
昼間もピアノの練習をしていたは、ジーナに声をかけられて休憩の為にテラスにやって来たが楽譜はその膝の上に置いたままだった。
唐突に悪態をついたにジーナはけして気を悪くした様子はなく、くすくすと笑ってこちらを見ている。
「……あの人、俺のこと心配しすぎなんじゃないの」
「フェラーリンのことね」
名前を言いたくなかったので、ふいっとそっぽを向く。
「これおいしい」
そしてクッキーを摘んで涼しい顔をした。
ぱらぱらと楽譜にこぼした食べかすは後で纏めて払おうと一瞥する。
「そう、よかったわ。…………彼はあなたのことが心配なのよ」
「その心配にこたえて、軍から出て行ってやったんじゃないか」
「どこにいても、何をしていても、愛しい人には心を配るものよ」
ふふっと笑うジーナに、はそっと頬を膨らます。
「愛しいもんか」
「あら、なぜそう思うの」
思いを伝えたとか、好きだった、なんて話はしたこともないが、ジーナは全て分かっているような顔をして頬杖をついて訊ねる。
「愛してるなら傍に置いてほしかった」
クッキーを真ん中でそっと折る。ひとかけらを口に放り込み、もうひとかけらはソーサーの端に置いてティーカップの中の紅茶をスプーンでくるりと掻き混ぜた。
「それはあなただけの愛し方よ」
「僕だけ?」
「ええ、そう。他の人もそういう愛し方はするけれど、フェラーリンの愛し方とは違うのかもしれないわ」
「傍に居なくても平気な人って、いるんだね」
「そうね。でも彼の場合平気とは限らないかもしれない」
「じゃあなんで」
「は相変わらず子供ねえ」
なんでなんで、と聞いてばかり居るからだろうか、ジーナはにんまりと笑う。
彼女がを馬鹿にしたことは過去になく、そう言われても悪い気はしない。けれど今回ばかりはもふてくされた。好きな人の考えが読めず、他人に聞くというのはそれなりに悔しいものだ。
「愛も知らないって?」
「いいえ、子供でも愛は知ってる。も愛することは知ってるじゃない」
はよくわからなくて、首を傾げたままもうひとかけらのクッキーを食べた。
あのセリフで終わらせたくせにまだ続きがあるという後だしなアレですが、眠るよっていうのはこういう意味だとやっぱり言葉にしておくべきかなって思って。迷いましたが。
世界から拒絶されたような気がした。
ぎこちなく笑うだが、今にも泣きだしてしまいそうな顔をしている。
ただでさえ憔悴していたのに、この言葉はとても堪えた。
仲間を戦場や訓練に送り出す度、食事が喉を通らなくなりそうだったがチョコレートを口に含んでなんとか脳や胃を刺激して、寝付けない夜でも疲れて眠り落ちるまでじっと耐えた。
明日はフェラーリンに会える。
彼の飛行艇を整備しよう。
おはよう、と言ってもらえたらいい。
こんな風に希望を胸に抱いて眠る為には、フェラーリンの存在が必要不可欠だった。
軍を裏切ることはできない、とは思っていない。たとえば、マルコではなくフェラーリンが退役するのなら、迷わず自分も軍の整備士を辞めてジーナの店の手伝いをしながら、時折フェラーリンがやってきてくれないかとピアノを弾きながら待つだろう。
だから充分、自分の欲望に忠実に生きている。
心配されても、追い出されたくはなかった。
「もし……俺が帰って来なかったらどうする」
フェラーリンの悲しそうな顔を見て、昂りがすっと冷めて行く。
けれど溢れ出た涙が目の奥に戻るわけがなく、眼窩に溜まる水分は今にも零れそうに揺れていた。
それはずっと考えていたことだった。否、考える必要もなかった。
「―――眠るよ」
彼が帰らぬ人となったら、酷く傷つき、起きてすらいられないだろう。
瞬きと同時に涙が落ちて鎖骨に跳ねた。
「二度と目を覚ますことがないように」
なにも、怖いことなどない。
フェラーリンは目を見開いて、肩を掴む手を少し緩める。けれどそれは離れて行かず、首と顎を伝って耳の下や後ろを撫でた。心地良いと思いながら、近づいて来る顔を眺めて目を瞑る。
呼吸を止めるのはほんの数秒でよかった。
音もなく触れ合った唇は、離れたと同時に熱い息を零す。薄目で彼の開いた口を眺めて、顔をすり寄せてもう一度と強請ると、息を飲み込むような音を立てて再び口を塞がれた。
廊下ですることではないと互いに思っていたので、自然と体は動いて廊下の影に潜む。
放さないとばかりに後頭部と腰を押さえる手も、甘えるように首筋と米神をくすぐる手も、触れているところの全てが熱い。
「……」
呼吸のついでに愛称を呼ばれると照れくさくて、唇を啄み返事の代わりにする。
今度はが名前を呼ぼうとすれば、声にする前に飲み込まれた。
程なくして、人の足音や気配がしたので離れて、襟や髪を整え、言葉もなく二人は別れた。
は家に帰って、フェラーリンの言葉を反芻して涙を零した。エドモンドが死んだと受け止めたときよりも、長く長く。
キスよりも言われた言葉の方が重たい。
どちらも、嘘ではないのだ。フェラーリンはを思って言ってくれて、してくれた。
彼の気持ちも分かる。けれど。
一晩泣いて、次の日にははこっそりと辞表を出し、荷物をまとめて部屋を出ていった。
誰にも会わず、半ば逃げるように姿を消したが辞表を見た者はおそらく納得し、追いかけてくることはないだろう。
マルコのように、賞金稼ぎなんかをしていなければ。
はまずジーナの店に行った。軍を辞めたと言うと、彼女はそれ以上聞かずにに一室用意して、一週間近くバカンスのようなのんびりとした生活を提供してくれた。料金は支払うと最初言ったのだが、店で演奏してくれれば良いと言われたのではあっさりと頷いた。店内ではずっと演奏し続けていれば挨拶にまわることもなく、ただ没頭できる。ピアノを弾いているところを邪魔をして来る客はジーナの店にはいない。
軍の関係者が店に顔を出す事は稀だったが、数人は来るものでの姿を見ると少し驚いたようだった。けれど誰も演奏を中断させることなく帰って行った。
数日するとフェラーリンが顔を出したが、は無視してピアノを引き続けた。
それは、彼がそう望んだことだ。こうして、のんびりピアノを弾いている生活を送ってほしいと思っているのだろう。そう言いたげに、は視線を一向にやらなかった。やはりフェラーリンは声をかけずに帰って行き、それでも週に一度くらいの頻度でやって来た。
「なんか、もう、鬱陶しい」
「なあに?急にふてくされて」
昼間もピアノの練習をしていたは、ジーナに声をかけられて休憩の為にテラスにやって来たが楽譜はその膝の上に置いたままだった。
唐突に悪態をついたにジーナはけして気を悪くした様子はなく、くすくすと笑ってこちらを見ている。
「……あの人、俺のこと心配しすぎなんじゃないの」
「フェラーリンのことね」
名前を言いたくなかったので、ふいっとそっぽを向く。
「これおいしい」
そしてクッキーを摘んで涼しい顔をした。
ぱらぱらと楽譜にこぼした食べかすは後で纏めて払おうと一瞥する。
「そう、よかったわ。…………彼はあなたのことが心配なのよ」
「その心配にこたえて、軍から出て行ってやったんじゃないか」
「どこにいても、何をしていても、愛しい人には心を配るものよ」
ふふっと笑うジーナに、はそっと頬を膨らます。
「愛しいもんか」
「あら、なぜそう思うの」
思いを伝えたとか、好きだった、なんて話はしたこともないが、ジーナは全て分かっているような顔をして頬杖をついて訊ねる。
「愛してるなら傍に置いてほしかった」
クッキーを真ん中でそっと折る。ひとかけらを口に放り込み、もうひとかけらはソーサーの端に置いてティーカップの中の紅茶をスプーンでくるりと掻き混ぜた。
「それはあなただけの愛し方よ」
「僕だけ?」
「ええ、そう。他の人もそういう愛し方はするけれど、フェラーリンの愛し方とは違うのかもしれないわ」
「傍に居なくても平気な人って、いるんだね」
「そうね。でも彼の場合平気とは限らないかもしれない」
「じゃあなんで」
「は相変わらず子供ねえ」
なんでなんで、と聞いてばかり居るからだろうか、ジーナはにんまりと笑う。
彼女がを馬鹿にしたことは過去になく、そう言われても悪い気はしない。けれど今回ばかりはもふてくされた。好きな人の考えが読めず、他人に聞くというのはそれなりに悔しいものだ。
「愛も知らないって?」
「いいえ、子供でも愛は知ってる。も愛することは知ってるじゃない」
はよくわからなくて、首を傾げたままもうひとかけらのクッキーを食べた。
あのセリフで終わらせたくせにまだ続きがあるという後だしなアレですが、眠るよっていうのはこういう意味だとやっぱり言葉にしておくべきかなって思って。迷いましたが。
キスしたからって想いが通じあってハッピーエンドって訳じゃないし、むしろ軍を辞めた方が良いと言われた事の方がやっぱり大きいと思います。だから軍はやめます。
2016/05/20
![]()
![]()
![]()
Title
by
yaku 30
no uso