
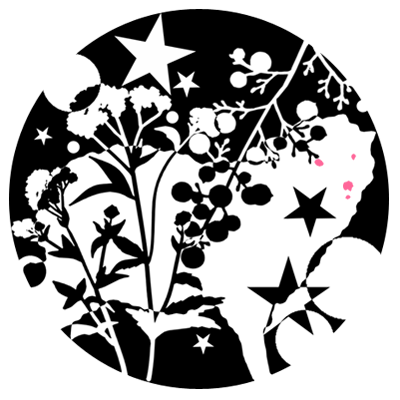
百年前の恋人
昨日分け合った熱は、消えていた。
誰も、彼が去ったことに驚かず、フェラーリンが知ったのは昼になって彼の姿を探した時だった。同じく整備士で、をよくカフェに連れ出しランチをとらせていた男が、顔を出しに来たフェラーリンに苦笑しながら、が辞めたことを教えてくれた。
丁度傍に居た彼の上司に詳細を問えば、朝出勤したら机の上に辞表が置いてあったそうだ。
辞めるだろう、辞めた方がいいだろう、と、彼の繊細さを知っていた仲間達は思っていた。
フェラーリンだって、そう思ってすすめたはずだった。
けれど、もう居ないと思うとやはり苦々しい顔を浮かべてしまい、同僚やの仕事仲間には、彼を怒らないでやってくれと頼まれてしまう。
怒りはない。傍に居ない事が不満なだけだ。
―――僕はただあなたのそばにいたかった……。
脳裏にこびりつく、掠れた声。
瞼に焼きついた、海色の濡れた瞳。
唇には一切残っていない、熱と吐息。
手を伸ばしても、部屋を探しても、どこにも居ない。傍に居たいと言った言葉に、嘘はないはずだ。けれどフェラーリンが軍を辞めた方が良いとすすめた所為であっさりと彼は出て行った。
昨日の自分に、嫌気がさす。
どんなに辛い思いをしていようが、眠れなかろうが、生きている限り隣にいさせてやればよかったのだ。寂しいならキスを、眠れないなら子守唄を、傍らにいて送る、そんな生活を。
傍に居ない事がこんなにも辛いとは思わなかった。
フェラーリンは強く拳をにぎり、なんとか仕事に戻る。戦争はまだ、終わっていないのだ。
長い遠征から帰って来ると、同僚からがジーナの店でのんびりピアノを弾いて過ごしている噂を聞いた。
連れ戻すなんていわないよな、と問われてもちろんだと答えたが、正直のところには本当は帰って来てほしかった。
けれど店でピアノを引いている彼の横顔を眺めて、酒を飲んで、食事をとって、ああもういいかと思った。
会いにくれば良いのだ、この店に。
は軍には居ないけれど、この店に居て、夜を纏い優しい音色を奏で、慕う女性の元で健やかに暮らしている。
目が合うことも、頭を撫でることも、会話をする事もできないけれど、フェラーリンはひとまず、この姿を見るだけでなんとかやって行こうと彼のために思い直した。
ところが一ヶ月がすぎると、はまた姿を消した。
何度来てもが店に居ないことに困惑しているフェラーリンをジーナは察したようで、ある日店のスタッフに案内されて個室へ通された。
そこには、小さなが若い人間だったころのマルコにしがみついて、他の幼馴染み達と一緒に笑っている写真があるだけで、当の本人はいない。
「可愛いでしょう、」
「ああ……」
写真を眺めていたフェラーリンの元へ、ジーナはやって来た。
「……はどうしたんだ?体調を崩してるのか?」
「は元気よ、きっと」
「きっと?ここにはいないのか?まさかマルコの所へ?」
「マルコもさすがには連れ回さないわ」
狼狽えているフェラーリンが面白いのか、ジーナはころころ笑った。
今更一緒に賞金稼ぎをするくらいなら最初から着いて行ってるだろう、とジーナもフェラーリンも口にしないまま結論づけて頷く。
「それで、はどこに?」
「会いに行くの?」
「……顔くらい、見に行ったっていいだろう」
「そうね。でもごめんなさいね、私はがどこに居るのか知らないの」
フェラーリンは目を剥いた。
一番の体調を気遣っていたジーナのセリフとは思えない。けれど何の心配もしていないという朗らかな顔を見て、もジーナも納得して別れたことは分かった。
もう一ヶ月もの姿を見ていないフェラーリンは、深くため息を吐いて痛む米神を指先で撫でる。
「やっぱり、飛行艇が好きなんですって」
「……でも、軍には」
「ええ、戻らないでしょうね。もちろん、マルコにくっついてるわけでもないけど」
フェラーリンは店を後にした。
会いたい、探したい、連れ戻したい、というのはフェラーリンの忠実な欲望なのだが、実の所は軍に居ない方が良いし、自分と離れて過ごして自分の死や危険を知れないような所に居た方が良いと思っていた。
今はどうだか自信がないので分からないが、軍に居てフェラーリンが死んだら、は永い眠りについてしまう。
それだけは、どうか辞めてほしい。
「たった、一ヶ月でこれか……」
ぐるぐるとのことばかり考える自分に、自嘲して笑った。
あれから、三年の月日が流れた。
なんとか調子を取り戻したし、戦争があったり、訓練で死にかけたりしたけれど、いつもの日常は流れていた。
昇進もして、生活は前よりも安定したようにも思う。
ジーナとの友好は続き、連絡を入れる日もあれば、店に会いに行く日もある。
はよりによって、フェラーリンが店にくる直前や直後にジーナに会いに来ているようで、ジーナからは見事にすれ違っていると笑われた。
「けれど、まだ会わないでも良いみたいね」
「何?」
「の方がね、フェラーリンは居ないかって警戒してるのよ」
「なぜ……」
ショックだった。軍から追い出したのは自分なのだが、あの日、傍にいたいと、後を追うと泣いてくれた筈なのに。
唇の熱は記憶の彼方に行ってしまったが、魅力と甘さはおぼえていて、何度も思い出そうと躍起になった。
三年間、彼を忘れた事などない。
「でも警戒してるってことは、思われてるわ」
落ち込みそうになって額を抑えたフェラーリンにジーナは笑う。
どういうことだと言いたげに、彼女の顔を見ると更に笑みを濃くした。
「あの子っていつまでも子供っぽいのよ」
「そうか」
フェラーリンはあまり、に子供みたいな所を見せてもらった事がない。
最後の日、口喧嘩のような言い合いをしたときは少し素が見えた。撫でてほしがることと、キスをしている時の甘えた仕草なら知っているが、本当にそれだけで、彼の考えまでは察する事が出来ずにいる。
結局、フェラーリンが言っただけで軍を辞めてしまった理由も、まだ理解できていない。
「俺は……」
「会いたい?」
ジーナが覗き込んで来る瞳を見返す。
が会う事を望んでいないのに、自分で会いたいと言うのは格好悪く思えた。もし言うなら、会って、会いたかったと本人に言いたい。
「君に言うのはよそう」
「そうね。に言ってやってちょうだい」
「そのがどこにいるかは分からないんだがな」
「あら、意外とすぐそこに居るんじゃないかしら」
「ジーナ、本当は知ってるんじゃないか?」
「いいえ、本当に知らないのよ」
主人公出て来ないし、二話にわたり子供っぽいと言われる。
誰も、彼が去ったことに驚かず、フェラーリンが知ったのは昼になって彼の姿を探した時だった。同じく整備士で、をよくカフェに連れ出しランチをとらせていた男が、顔を出しに来たフェラーリンに苦笑しながら、が辞めたことを教えてくれた。
丁度傍に居た彼の上司に詳細を問えば、朝出勤したら机の上に辞表が置いてあったそうだ。
辞めるだろう、辞めた方がいいだろう、と、彼の繊細さを知っていた仲間達は思っていた。
フェラーリンだって、そう思ってすすめたはずだった。
けれど、もう居ないと思うとやはり苦々しい顔を浮かべてしまい、同僚やの仕事仲間には、彼を怒らないでやってくれと頼まれてしまう。
怒りはない。傍に居ない事が不満なだけだ。
―――僕はただあなたのそばにいたかった……。
脳裏にこびりつく、掠れた声。
瞼に焼きついた、海色の濡れた瞳。
唇には一切残っていない、熱と吐息。
手を伸ばしても、部屋を探しても、どこにも居ない。傍に居たいと言った言葉に、嘘はないはずだ。けれどフェラーリンが軍を辞めた方が良いとすすめた所為であっさりと彼は出て行った。
昨日の自分に、嫌気がさす。
どんなに辛い思いをしていようが、眠れなかろうが、生きている限り隣にいさせてやればよかったのだ。寂しいならキスを、眠れないなら子守唄を、傍らにいて送る、そんな生活を。
傍に居ない事がこんなにも辛いとは思わなかった。
フェラーリンは強く拳をにぎり、なんとか仕事に戻る。戦争はまだ、終わっていないのだ。
長い遠征から帰って来ると、同僚からがジーナの店でのんびりピアノを弾いて過ごしている噂を聞いた。
連れ戻すなんていわないよな、と問われてもちろんだと答えたが、正直のところには本当は帰って来てほしかった。
けれど店でピアノを引いている彼の横顔を眺めて、酒を飲んで、食事をとって、ああもういいかと思った。
会いにくれば良いのだ、この店に。
は軍には居ないけれど、この店に居て、夜を纏い優しい音色を奏で、慕う女性の元で健やかに暮らしている。
目が合うことも、頭を撫でることも、会話をする事もできないけれど、フェラーリンはひとまず、この姿を見るだけでなんとかやって行こうと彼のために思い直した。
ところが一ヶ月がすぎると、はまた姿を消した。
何度来てもが店に居ないことに困惑しているフェラーリンをジーナは察したようで、ある日店のスタッフに案内されて個室へ通された。
そこには、小さなが若い人間だったころのマルコにしがみついて、他の幼馴染み達と一緒に笑っている写真があるだけで、当の本人はいない。
「可愛いでしょう、」
「ああ……」
写真を眺めていたフェラーリンの元へ、ジーナはやって来た。
「……はどうしたんだ?体調を崩してるのか?」
「は元気よ、きっと」
「きっと?ここにはいないのか?まさかマルコの所へ?」
「マルコもさすがには連れ回さないわ」
狼狽えているフェラーリンが面白いのか、ジーナはころころ笑った。
今更一緒に賞金稼ぎをするくらいなら最初から着いて行ってるだろう、とジーナもフェラーリンも口にしないまま結論づけて頷く。
「それで、はどこに?」
「会いに行くの?」
「……顔くらい、見に行ったっていいだろう」
「そうね。でもごめんなさいね、私はがどこに居るのか知らないの」
フェラーリンは目を剥いた。
一番の体調を気遣っていたジーナのセリフとは思えない。けれど何の心配もしていないという朗らかな顔を見て、もジーナも納得して別れたことは分かった。
もう一ヶ月もの姿を見ていないフェラーリンは、深くため息を吐いて痛む米神を指先で撫でる。
「やっぱり、飛行艇が好きなんですって」
「……でも、軍には」
「ええ、戻らないでしょうね。もちろん、マルコにくっついてるわけでもないけど」
フェラーリンは店を後にした。
会いたい、探したい、連れ戻したい、というのはフェラーリンの忠実な欲望なのだが、実の所は軍に居ない方が良いし、自分と離れて過ごして自分の死や危険を知れないような所に居た方が良いと思っていた。
今はどうだか自信がないので分からないが、軍に居てフェラーリンが死んだら、は永い眠りについてしまう。
それだけは、どうか辞めてほしい。
「たった、一ヶ月でこれか……」
ぐるぐるとのことばかり考える自分に、自嘲して笑った。
あれから、三年の月日が流れた。
なんとか調子を取り戻したし、戦争があったり、訓練で死にかけたりしたけれど、いつもの日常は流れていた。
昇進もして、生活は前よりも安定したようにも思う。
ジーナとの友好は続き、連絡を入れる日もあれば、店に会いに行く日もある。
はよりによって、フェラーリンが店にくる直前や直後にジーナに会いに来ているようで、ジーナからは見事にすれ違っていると笑われた。
「けれど、まだ会わないでも良いみたいね」
「何?」
「の方がね、フェラーリンは居ないかって警戒してるのよ」
「なぜ……」
ショックだった。軍から追い出したのは自分なのだが、あの日、傍にいたいと、後を追うと泣いてくれた筈なのに。
唇の熱は記憶の彼方に行ってしまったが、魅力と甘さはおぼえていて、何度も思い出そうと躍起になった。
三年間、彼を忘れた事などない。
「でも警戒してるってことは、思われてるわ」
落ち込みそうになって額を抑えたフェラーリンにジーナは笑う。
どういうことだと言いたげに、彼女の顔を見ると更に笑みを濃くした。
「あの子っていつまでも子供っぽいのよ」
「そうか」
フェラーリンはあまり、に子供みたいな所を見せてもらった事がない。
最後の日、口喧嘩のような言い合いをしたときは少し素が見えた。撫でてほしがることと、キスをしている時の甘えた仕草なら知っているが、本当にそれだけで、彼の考えまでは察する事が出来ずにいる。
結局、フェラーリンが言っただけで軍を辞めてしまった理由も、まだ理解できていない。
「俺は……」
「会いたい?」
ジーナが覗き込んで来る瞳を見返す。
が会う事を望んでいないのに、自分で会いたいと言うのは格好悪く思えた。もし言うなら、会って、会いたかったと本人に言いたい。
「君に言うのはよそう」
「そうね。に言ってやってちょうだい」
「そのがどこにいるかは分からないんだがな」
「あら、意外とすぐそこに居るんじゃないかしら」
「ジーナ、本当は知ってるんじゃないか?」
「いいえ、本当に知らないのよ」
主人公出て来ないし、二話にわたり子供っぽいと言われる。
子供に含まれる意味は違うんですけど。
出て行った方が良い、と言ったフェラーリンの方が参ってたら良いな。もう百年も会っていないような気分で。
2016/05/20
![]()
![]()
![]()
Title
by
yaku 30
no uso