
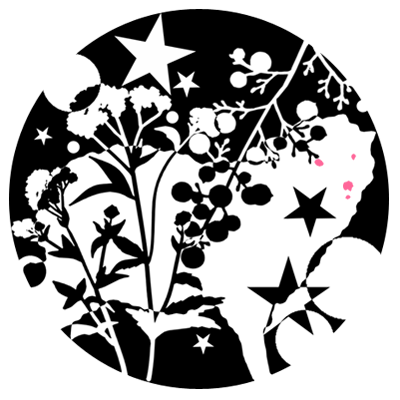
魚たちの目眩
は少しばかりいけないことをしたので、身を隠していた。
真っ先に頼るのはやはり幼い頃から母のように姉のように自分の面倒を見てくれた彼女で、自分では飛行艇を運転せずに、久々にホテルアドリアーノを訪れた。
「いらっしゃい、久しぶりね。また休暇が取れたの?」
「そんなところ」
急な来訪でもジーナは驚かなかった。
ホテルのフロントではすぐに部屋を開ける手配をしてくれているので、もうの荷物は運び込まれている。
「ミラノの飛行艇製造会社に居たんだけど」
「!……ええ」
ジーナには今までどこにいるとは言わなかったため、一瞬目を見開いたけれど、彼女はすぐに穏やかな笑みを浮かべて、の言葉を待った。
「マルコの飛行艇を直したんだ」
「まあ……じゃあ電話で言っていたのって」
「聞いてたんだね」
「のことはちっとも」
「そっか」
静かに食事を続けながら、は視線を落とす。
「なんで僕の行き先をマルコに聞かないでいてくれたの」
「あなたが秘密を望んだからよ」
ひとえにフェラーリンに行き先を教えたくなかっただけなのだが、ジーナはそれ以上に気持ちを汲んで黙って待っていてくれたらしい。
「僕がジーナに秘密を作って、寂しいとは思わなかった?」
「思わないわ」
今までは何だって、ジーナやマルコ、それだけではなく色々な人に相談してきた。なんとかしてくれると思っていたからだ。
大人になるにつれて、どうにもならないことや、相談もしないことが増えたが、そうだとしても本当に言えないことや言いたくないことなんてなかった。
「の顔を見れば、元気なことくらいわかるもの。だからどんなに秘密を持っていたって私は良いの」
得意気に笑うジーナを見て、も笑った。
次の日は庭で各々過ごしていた。
ジーナはガゼボでお茶を飲みながら本を読んでいる。
は石塀に肘をついてぼんやりと海を眺めていたけれど、ふいに他人の声が聞こえてジーナのいるガゼボを見上げる。
「ジーナ、一緒にハリウッドへいこう。――――空賊の用心棒なぞ金と名声のほんのワンステップさ」
プライベートな庭へ勝手に侵入して来た男は、マルコの言っていたアメリカのカーチスだとすぐに理解する。
「次はハリウッドの大スターだ」
「その次は?」
「大統領!」
その言葉に、ジーナは大笑いをしている。
は心配する必要はなさそうだと思い、塀に背中を預けた。
「――――でも駄目、私いま賭けをしているから」
カーチスは何かを言いたげに口ごもるが、ジーナはさらに言葉を紡ぐ。
「私がこの庭に居る時、その人が訪ねて来たら、今度こそ愛そうって賭けしてるの。でもその馬鹿、夜のお店にしかこないわ。――――日差しの中へはちっとも出て来ない」
その時、エンジン音がした。
ジーナはのいるところへ、階段を駆け下りてやってくる。そして赤い飛行艇をみとめて、ただただ見つめる。
初めて賭けの話を聞いたが、きっとそれはマルコのことなのだろう。
マルコの言葉のない挨拶と、ジーナの待つ後ろ姿を眺めて胸が震えた。
「人の事言えないじゃないか、ジーナ」
小さな呟きはエンジンの音に紛れて、誰の耳にも届かなかった。
それから数日後、マルコとカーチスのリターンマッチの噂を聞いた。
その日はもこっそり夜の店に出ていたのだ。
リターンマッチをすることは、ジーナもわかっていたようで後で日付を教えると頭を抱えていた。
「本当にやる気なのね」
「勝負の賭け金が、フィオらしいんだ」
「フィオ?」
「マルコの飛行艇を作った女の子。社長の孫娘」
「まあ」
フィオの話をすると、ジーナは少し興味深そうな表情をした。もっと話して、と笑うのでは待ってましたとばかりにフィオの話をした。
自分をここまで引っ張り上げてくれたのも、マルコの飛行艇が素晴らしくなったのも、みんな彼女のおかげだろうと。
「素敵な子」
「うん、素敵だよ」
「珍しいのね、女の子をそんな風に褒めるなんて」
「え?」
「って昔から女の子は苦手じゃない」
「フィオはなんだか、女の子っていう気がしないんだよね」
「それ本人に言ってないでしょうね」
「もちろん!っていうか、僕がそう思ってるだけで、客観的に見たらフィオはちゃんと女の子だと思う」
ジーナとこんな風にたくさん話をするように、フィオともたくさん話をした。
ゆっくりと聞いてくれるジーナとは違い、フィオははっきりとしていて続きを促したり、自分の話もしてくれた。だからとても、会話が弾んだ記憶がある。
もちろん、ジーナに不満があるわけではないのだが。
「フィオには何でも話せる。……僕、友達なんだ」
「よかったわね、」
「フィオだけじゃなくて、みんなの事が大好き」
頬杖をつく体勢をやめて、腕を組みそこに頭を乗せる。はまるで寝転がるように傾けて、ジーナを見上げた。
夜の店に長く居た所為か、眠いのかもしれない。
やがて、うっとりするように目を瞑って、ふわりと口元を緩めた。
「長い事、寂しいと思わなかった」
「……ええ」
目を瞑ったまま話し始めるに、ジーナはゆっくりと手を伸ばして、長い前髪を退ける。髪の毛と同じ色をした睫毛がふわりと揺れて、一瞬だけ目がきつく閉じられたがやはりすぐに気持ちの良さそうな顔に戻る。
「死んでしまった友達も、生きている友達も、僕のそばに居てくれたから」
「そう」
「会えなくても、平気だった」
唇の動きはどんどん遅くなり、声も小さくなって行くけれど、ジーナは静かな部屋の中での囁く言葉を聞いた。
――――……僕の愛し方は変わったみたい。
この話考えて映画を見ているときから、ジーナのお庭に居る主人公良いなって思ってたんですが、それをしれっと書くことが出来て楽しかったです。この時のこのシーンで、居させたかったなっていううろ覚えの……四年前の野望(?)
真っ先に頼るのはやはり幼い頃から母のように姉のように自分の面倒を見てくれた彼女で、自分では飛行艇を運転せずに、久々にホテルアドリアーノを訪れた。
「いらっしゃい、久しぶりね。また休暇が取れたの?」
「そんなところ」
急な来訪でもジーナは驚かなかった。
ホテルのフロントではすぐに部屋を開ける手配をしてくれているので、もうの荷物は運び込まれている。
「ミラノの飛行艇製造会社に居たんだけど」
「!……ええ」
ジーナには今までどこにいるとは言わなかったため、一瞬目を見開いたけれど、彼女はすぐに穏やかな笑みを浮かべて、の言葉を待った。
「マルコの飛行艇を直したんだ」
「まあ……じゃあ電話で言っていたのって」
「聞いてたんだね」
「のことはちっとも」
「そっか」
静かに食事を続けながら、は視線を落とす。
「なんで僕の行き先をマルコに聞かないでいてくれたの」
「あなたが秘密を望んだからよ」
ひとえにフェラーリンに行き先を教えたくなかっただけなのだが、ジーナはそれ以上に気持ちを汲んで黙って待っていてくれたらしい。
「僕がジーナに秘密を作って、寂しいとは思わなかった?」
「思わないわ」
今までは何だって、ジーナやマルコ、それだけではなく色々な人に相談してきた。なんとかしてくれると思っていたからだ。
大人になるにつれて、どうにもならないことや、相談もしないことが増えたが、そうだとしても本当に言えないことや言いたくないことなんてなかった。
「の顔を見れば、元気なことくらいわかるもの。だからどんなに秘密を持っていたって私は良いの」
得意気に笑うジーナを見て、も笑った。
次の日は庭で各々過ごしていた。
ジーナはガゼボでお茶を飲みながら本を読んでいる。
は石塀に肘をついてぼんやりと海を眺めていたけれど、ふいに他人の声が聞こえてジーナのいるガゼボを見上げる。
「ジーナ、一緒にハリウッドへいこう。――――空賊の用心棒なぞ金と名声のほんのワンステップさ」
プライベートな庭へ勝手に侵入して来た男は、マルコの言っていたアメリカのカーチスだとすぐに理解する。
「次はハリウッドの大スターだ」
「その次は?」
「大統領!」
その言葉に、ジーナは大笑いをしている。
は心配する必要はなさそうだと思い、塀に背中を預けた。
「――――でも駄目、私いま賭けをしているから」
カーチスは何かを言いたげに口ごもるが、ジーナはさらに言葉を紡ぐ。
「私がこの庭に居る時、その人が訪ねて来たら、今度こそ愛そうって賭けしてるの。でもその馬鹿、夜のお店にしかこないわ。――――日差しの中へはちっとも出て来ない」
その時、エンジン音がした。
ジーナはのいるところへ、階段を駆け下りてやってくる。そして赤い飛行艇をみとめて、ただただ見つめる。
初めて賭けの話を聞いたが、きっとそれはマルコのことなのだろう。
マルコの言葉のない挨拶と、ジーナの待つ後ろ姿を眺めて胸が震えた。
「人の事言えないじゃないか、ジーナ」
小さな呟きはエンジンの音に紛れて、誰の耳にも届かなかった。
それから数日後、マルコとカーチスのリターンマッチの噂を聞いた。
その日はもこっそり夜の店に出ていたのだ。
リターンマッチをすることは、ジーナもわかっていたようで後で日付を教えると頭を抱えていた。
「本当にやる気なのね」
「勝負の賭け金が、フィオらしいんだ」
「フィオ?」
「マルコの飛行艇を作った女の子。社長の孫娘」
「まあ」
フィオの話をすると、ジーナは少し興味深そうな表情をした。もっと話して、と笑うのでは待ってましたとばかりにフィオの話をした。
自分をここまで引っ張り上げてくれたのも、マルコの飛行艇が素晴らしくなったのも、みんな彼女のおかげだろうと。
「素敵な子」
「うん、素敵だよ」
「珍しいのね、女の子をそんな風に褒めるなんて」
「え?」
「って昔から女の子は苦手じゃない」
「フィオはなんだか、女の子っていう気がしないんだよね」
「それ本人に言ってないでしょうね」
「もちろん!っていうか、僕がそう思ってるだけで、客観的に見たらフィオはちゃんと女の子だと思う」
ジーナとこんな風にたくさん話をするように、フィオともたくさん話をした。
ゆっくりと聞いてくれるジーナとは違い、フィオははっきりとしていて続きを促したり、自分の話もしてくれた。だからとても、会話が弾んだ記憶がある。
もちろん、ジーナに不満があるわけではないのだが。
「フィオには何でも話せる。……僕、友達なんだ」
「よかったわね、」
「フィオだけじゃなくて、みんなの事が大好き」
頬杖をつく体勢をやめて、腕を組みそこに頭を乗せる。はまるで寝転がるように傾けて、ジーナを見上げた。
夜の店に長く居た所為か、眠いのかもしれない。
やがて、うっとりするように目を瞑って、ふわりと口元を緩めた。
「長い事、寂しいと思わなかった」
「……ええ」
目を瞑ったまま話し始めるに、ジーナはゆっくりと手を伸ばして、長い前髪を退ける。髪の毛と同じ色をした睫毛がふわりと揺れて、一瞬だけ目がきつく閉じられたがやはりすぐに気持ちの良さそうな顔に戻る。
「死んでしまった友達も、生きている友達も、僕のそばに居てくれたから」
「そう」
「会えなくても、平気だった」
唇の動きはどんどん遅くなり、声も小さくなって行くけれど、ジーナは静かな部屋の中での囁く言葉を聞いた。
――――……僕の愛し方は変わったみたい。
この話考えて映画を見ているときから、ジーナのお庭に居る主人公良いなって思ってたんですが、それをしれっと書くことが出来て楽しかったです。この時のこのシーンで、居させたかったなっていううろ覚えの……四年前の野望(?)
2016/11/12
![]()
![]()
![]()
Title
by
yaku 30
no uso