
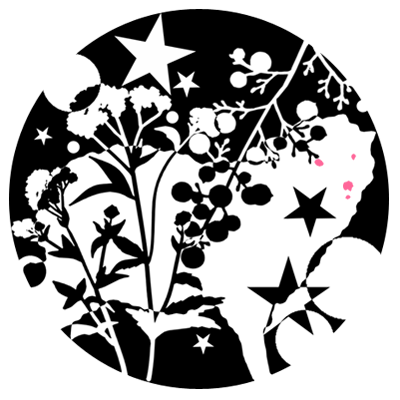
睡も甘いもこの声も
の名前がフェラーリンの耳をくすぐった。彼の重低音からくりだされるその響きは、どうしても苦手だと思う。ジーナの声で聞く事に違和感などないというのに。
おそらくそれが嫉妬だということは、わかっていてもみとめたくはない。みとめたところで、とマルコの長い付き合いと信頼は変わらない。そして、自分の思いも変わる事はない。
マルコはからかう為か、それとも責める気持ちがあってのことか、フェラーリンがしたことをつきつけた。
今その話をしている場合ではなく、出ようとする言い訳をなんとか飲み込んでから話を続けた。それきり、マルコはの話題をだすことはなかったのだが、去り際にまた引き止められた。
が元気そうにしていた、という報告は、純粋に喜べなかった。
それはよかった、などと嘯くことも出来ず、声を潜めてマルコに別れを告げる。
街中を歩きながら、フェラーリンは自分の眉間に妙な力が込められていたことに気づいて、指先でそこを撫でた。複雑な心中が顔にでていたようだ。
道行く人はフェラーリンのそんな顔など気に留める事もなかったが、嫉妬と恋慕に燃えた顔を晒して歩いていたことに、少し恥じ入る。
深く息を吐き、歩みを遅めた。空を見上げる余裕さえできるが、考えていることは、追われている戦友についてではない。
「いっそお前のことを恨みそうだ、」
清々しい程に晴れた空に恨み言を託しても、きっと彼には届かないのだろう。
飛行艇パイロットとして空と海の広さも美しさも知っているが、のいる空と繋がっているとは思えないし、彼の瞳より美しい海はないと思った。
豚に寄り添う真珠を見送ったあと、フェラーリンは久々にジーナの店に顔を出そうと思っていた。何度彼女の店に顔を出しても会いたい顔どころか、後ろ姿すら見ることがなく、過去の写真程度しかないのだが。
それでも手がかりはあの場所しかない。のことを存外知らないのもあるが、今まではそれで事足りていた。
店に行く度に、まず首を振られることに慣れてはいたが、希望は捨てきれない。また彼女の憂えた顔を見る事になるのかもしれないが、それでも行こうと思っていた矢先に空賊連中が馬鹿騒ぎを始めたとの情報が入って来た。
「なんだと……?」
「しかも、一方はマルコだって言うんだ……」
思わず仲間を睨みつけるが、その口から出た先日会ったばかりのマルコの名前を聞いて更に顔をしかめる。
いつもこうやって、が遠のく。
まるで運命が阻むように。
「近々バーに行って飲む予定だったが、無理そうだな。……断りの連絡を入れておくか……」
「そりゃ、残念だったな」
仲間はすぐに、ジーナのことに合点が行ったのかあまり残念がっていない顔で、フェラーリンの肩を叩く。
本当に、本当に行きたかったのだ、とは言わなかった。
空軍の出動は、無事空振りに終わった。フェラーリンがジーナに通信を入れたからだ。
急いで連絡を入れた後に、フェラーリンも何食わぬ顔で隊に加わり件の場所へ向かったが、二機の飛行艇が空軍を撹乱させるためだけに残っているだけで、話の分からない操縦士たちはまんまと撒かれていた。
フェラーリンはというと、まさかはマルコを見に来たついでに待ってはいないだろうな、と目を凝らした。もちろん彼はそんな考え無しな事をするタイプではない。不在に納得しながらも、やはり落胆した。
すれ違うことに慣れて来た所為で、もしかしたらさっきまでこの場所に居たかもしれないし、今ジーナのところに顔を出せば会えるのではないかと思った。
しかし全くその通りで、ジーナのホテルに身を寄せていたらしいは、マルコに付き添っていた少女を迎えに来ていたそうだと、後ほど聞いて頭を抱えたのだった。
「でも、は今うちの会社にはいないのよ?」
なぜか一段落ついた気持ちになって店を訪れるとその少女が居た。今、ホテルアドリアーノに泊まっているとのことだ。
彼女、フィオはマルコの飛行艇の製作者であり、整備や調整を請け負っていたがずっと賞金稼ぎとともに行動する事は出来ず、実家の飛行艇製造会社でまた働くらしい。
その会社にがいたということも知れたが、きょとんとした顔に言われて、またしても肩を落とす事になる。
もしかして一生会えない運命じゃないだろうな、と苦虫を噛み潰したような顔をしたフェラーリンを見てフィオは笑った。貝のように白くて綺麗な歯が見える程に。
「あなた、いじわるな人ね?が言ってたわ」
「いじわる?」
「これ以上は内緒だけど」
ふふふと笑うフィオに、もう少し聞かせてくれとせがむ自分はなんと情けない男だろうと思った。
けれど、どれだけに会えていないか。どれほど会いたいか。それを前にするとなりふり構っている方が馬鹿らしい。
どうせ周りの連中は酒を飲みながら談笑しているのだから、フェラーリンが少女にすがる滑稽な姿は誰も見ていない。
ところがフィオは、静かな所へ行こうと店を出た。
「とは、どんな話をしたかしら。―――そうね、飛行艇がなにより好きって話だったわ」
彼女の思い出話は明るい声色で始まった。
「の過去もよくわからないけど、軍を辞めたのよね、彼って。それでここで働いてた。……そこそこ楽しい日々だったって言ってた」
けれど、飛行艇がなにより好き、という話をしたこと、事実彼女の会社で働いていた事で、楽しい日々を蹴って出て行ったことは言葉にしなくてもわかった。
「でもあなたの顔は忘れないんですって」
「……」
明朗快活な彼女はいつの間にか落ち着いた口調になっていた。海を撫でる風のような声と、波がおりなす泡のようにすぐ消えてしまいそうな言葉。それをたぐり寄せたくとも、手にすることは出来ない。
この耳でしかと聞いたつもりでも、今のが本物であったかを証明するものは何もなかった。
「に会いに行って、ミスター・フェラーリン」
「……でも、どこに居るのかが分からないんだ」
「うーん、困ったわね。のおうちは訪ねてみた?」
「彼は軍の寄宿舎に住んでいたし、君の所も住み込みだろう?もともとは祖母と暮らしていて、軍に入ってすぐ亡くな―――」
実家というものはない、と考えていた。けれど、故郷を探した事は一度もなかった。
軍に居たころから里帰りと称してこのホテルに滞在していたものだから、ここに帰って来ていると認識していたが違うかもしれない。
「ありがとう、フィオ」
「お礼を言われるような事、言ったかしら?」
「おおいに。の話をしてくれた―――それだけでも」
「素敵……」
フィオは柔らかく笑って、別れの礼をとるフェラーリンに手を振った。
「お幸せに!」
今度こそ、そうなれることを祈ろうと思った。
彼女は幸運の女神のようだから、きっとそのエールがあれば、幸せになれるような気がした。
素敵……っていうセリフ、フィオは意識せずに言っていて、どれだけすれ違っていても、互いを想っている二人は素敵っていう共通点みたいなものを。
おそらくそれが嫉妬だということは、わかっていてもみとめたくはない。みとめたところで、とマルコの長い付き合いと信頼は変わらない。そして、自分の思いも変わる事はない。
マルコはからかう為か、それとも責める気持ちがあってのことか、フェラーリンがしたことをつきつけた。
今その話をしている場合ではなく、出ようとする言い訳をなんとか飲み込んでから話を続けた。それきり、マルコはの話題をだすことはなかったのだが、去り際にまた引き止められた。
が元気そうにしていた、という報告は、純粋に喜べなかった。
それはよかった、などと嘯くことも出来ず、声を潜めてマルコに別れを告げる。
街中を歩きながら、フェラーリンは自分の眉間に妙な力が込められていたことに気づいて、指先でそこを撫でた。複雑な心中が顔にでていたようだ。
道行く人はフェラーリンのそんな顔など気に留める事もなかったが、嫉妬と恋慕に燃えた顔を晒して歩いていたことに、少し恥じ入る。
深く息を吐き、歩みを遅めた。空を見上げる余裕さえできるが、考えていることは、追われている戦友についてではない。
「いっそお前のことを恨みそうだ、」
清々しい程に晴れた空に恨み言を託しても、きっと彼には届かないのだろう。
飛行艇パイロットとして空と海の広さも美しさも知っているが、のいる空と繋がっているとは思えないし、彼の瞳より美しい海はないと思った。
豚に寄り添う真珠を見送ったあと、フェラーリンは久々にジーナの店に顔を出そうと思っていた。何度彼女の店に顔を出しても会いたい顔どころか、後ろ姿すら見ることがなく、過去の写真程度しかないのだが。
それでも手がかりはあの場所しかない。のことを存外知らないのもあるが、今まではそれで事足りていた。
店に行く度に、まず首を振られることに慣れてはいたが、希望は捨てきれない。また彼女の憂えた顔を見る事になるのかもしれないが、それでも行こうと思っていた矢先に空賊連中が馬鹿騒ぎを始めたとの情報が入って来た。
「なんだと……?」
「しかも、一方はマルコだって言うんだ……」
思わず仲間を睨みつけるが、その口から出た先日会ったばかりのマルコの名前を聞いて更に顔をしかめる。
いつもこうやって、が遠のく。
まるで運命が阻むように。
「近々バーに行って飲む予定だったが、無理そうだな。……断りの連絡を入れておくか……」
「そりゃ、残念だったな」
仲間はすぐに、ジーナのことに合点が行ったのかあまり残念がっていない顔で、フェラーリンの肩を叩く。
本当に、本当に行きたかったのだ、とは言わなかった。
空軍の出動は、無事空振りに終わった。フェラーリンがジーナに通信を入れたからだ。
急いで連絡を入れた後に、フェラーリンも何食わぬ顔で隊に加わり件の場所へ向かったが、二機の飛行艇が空軍を撹乱させるためだけに残っているだけで、話の分からない操縦士たちはまんまと撒かれていた。
フェラーリンはというと、まさかはマルコを見に来たついでに待ってはいないだろうな、と目を凝らした。もちろん彼はそんな考え無しな事をするタイプではない。不在に納得しながらも、やはり落胆した。
すれ違うことに慣れて来た所為で、もしかしたらさっきまでこの場所に居たかもしれないし、今ジーナのところに顔を出せば会えるのではないかと思った。
しかし全くその通りで、ジーナのホテルに身を寄せていたらしいは、マルコに付き添っていた少女を迎えに来ていたそうだと、後ほど聞いて頭を抱えたのだった。
「でも、は今うちの会社にはいないのよ?」
なぜか一段落ついた気持ちになって店を訪れるとその少女が居た。今、ホテルアドリアーノに泊まっているとのことだ。
彼女、フィオはマルコの飛行艇の製作者であり、整備や調整を請け負っていたがずっと賞金稼ぎとともに行動する事は出来ず、実家の飛行艇製造会社でまた働くらしい。
その会社にがいたということも知れたが、きょとんとした顔に言われて、またしても肩を落とす事になる。
もしかして一生会えない運命じゃないだろうな、と苦虫を噛み潰したような顔をしたフェラーリンを見てフィオは笑った。貝のように白くて綺麗な歯が見える程に。
「あなた、いじわるな人ね?が言ってたわ」
「いじわる?」
「これ以上は内緒だけど」
ふふふと笑うフィオに、もう少し聞かせてくれとせがむ自分はなんと情けない男だろうと思った。
けれど、どれだけに会えていないか。どれほど会いたいか。それを前にするとなりふり構っている方が馬鹿らしい。
どうせ周りの連中は酒を飲みながら談笑しているのだから、フェラーリンが少女にすがる滑稽な姿は誰も見ていない。
ところがフィオは、静かな所へ行こうと店を出た。
「とは、どんな話をしたかしら。―――そうね、飛行艇がなにより好きって話だったわ」
彼女の思い出話は明るい声色で始まった。
「の過去もよくわからないけど、軍を辞めたのよね、彼って。それでここで働いてた。……そこそこ楽しい日々だったって言ってた」
けれど、飛行艇がなにより好き、という話をしたこと、事実彼女の会社で働いていた事で、楽しい日々を蹴って出て行ったことは言葉にしなくてもわかった。
「でもあなたの顔は忘れないんですって」
「……」
明朗快活な彼女はいつの間にか落ち着いた口調になっていた。海を撫でる風のような声と、波がおりなす泡のようにすぐ消えてしまいそうな言葉。それをたぐり寄せたくとも、手にすることは出来ない。
この耳でしかと聞いたつもりでも、今のが本物であったかを証明するものは何もなかった。
「に会いに行って、ミスター・フェラーリン」
「……でも、どこに居るのかが分からないんだ」
「うーん、困ったわね。のおうちは訪ねてみた?」
「彼は軍の寄宿舎に住んでいたし、君の所も住み込みだろう?もともとは祖母と暮らしていて、軍に入ってすぐ亡くな―――」
実家というものはない、と考えていた。けれど、故郷を探した事は一度もなかった。
軍に居たころから里帰りと称してこのホテルに滞在していたものだから、ここに帰って来ていると認識していたが違うかもしれない。
「ありがとう、フィオ」
「お礼を言われるような事、言ったかしら?」
「おおいに。の話をしてくれた―――それだけでも」
「素敵……」
フィオは柔らかく笑って、別れの礼をとるフェラーリンに手を振った。
「お幸せに!」
今度こそ、そうなれることを祈ろうと思った。
彼女は幸運の女神のようだから、きっとそのエールがあれば、幸せになれるような気がした。
素敵……っていうセリフ、フィオは意識せずに言っていて、どれだけすれ違っていても、互いを想っている二人は素敵っていう共通点みたいなものを。
カーチスがジーナの賭けの話をマルコにするのと同じように、主人公のことをフィオが言ってしまうのも有りかなって。
2016/12/3
![]()
![]()
![]()
Title
by
yaku 30
no uso