
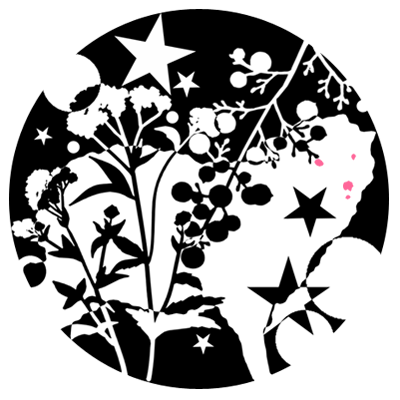
幸せならそれでいい
ジーナが所有する飛行艇を準備していたは、いつまでたってもやって来ない彼女を待っていた。
「まだかな、ジーナ」
「それが、お部屋に入ったっきりなんですよ」
風よけのフロントガラスに手をついて、嘆息した。
フィオの行く末が気になる事もあるが、カーチスとの戦いは純粋に見たかったのだ。
「おまたせ、急いで出して!」
「言われなくても!」
ジーナが駆け寄って来て、飛行艇に飛び乗った瞬間に発進させる。ぺろりと唇を舐めて上昇させるまでに、彼女が座ったことを確認するのも怠らない。
「イタリア空軍が出動するそうよ」
「フェラーリンさんから?」
「ええ、だから急いで」
「Si」
緊急性を理解し、は短く返事をして運転を始めた。
「もっと急げないの?」
「これでも一番早いんだって」
途中そんなやりとりをしながらも、まだ空軍の姿が見えないうちにリターンマッチが行われている孤島についた。
飛んでいる姿が見えない事で何故かと首をかしげたが、どうやらただの殴り合いに発展していたらしい。
人が沈んでいるであろう所の海面には白い気泡が浮かぶ。
はそんなものはお構いなしに着水した。このままだとマルコとカーチスの上に乗るが、そうなったらカウントをとっている男が引っ張り出せば良いだけの話だ。
「マルコ、マルコ聞いてる?」
飛行艇はなんとか、手前で停まる。否、停めてもらった。
「あなたもう一人女の子を不幸にする気なの?」
その口ぶりだとジーナが不幸なように聞こえる。
マルコが日差しのもとへ出て会いに来てくれるのを待っているのだから、そうではない今、幸せとは言い難い、という意味なのか。
喪失について共に悲しみに暮れて来たけれど、気丈に振る舞っていた彼女から出て来た、些細な本音にもどかしさを感じずにはいられない。自分が幸せにすることはできないのだが。
大量の泡を吐いたマルコが起き上がるのを待ち、カウントはナインのところで勿体ぶって止まった。
「ポルコ!!!!」
マルコが立ち上がると歓声がわいた。その中に可愛らしい声が混じる。
とジーナは安堵しながら、マルコとフィオが抱き合っているのを眺めた。やがてジーナはあたりの気を引き締めるように手を叩き、イタリア空軍がここに向かっていることをつげた。
後ろ暗い者達ばかりなので、クモの子を散らす様にそれぞれ逃げて行く。その様子は少し面白いとさえ思った。
も一応、捕まっては困るので早く帰りたい気持ちで一杯だ。
たとえ、彼がくるかもしれなくとも、ここでは会えない。
「お前はジーナの艇にのるんだ……!」
「いやよ!や!ポルコの艇にのる!パートナーだって言ったじゃない!」
「ジーナ、こいつをカタギの世界に戻してやってくれ」
「……ずるい人。いつもそうするのね」
「すまねえ、行ってくれ」
前の自分と似た境遇を感じながら、機体の中落とされたフィオを見る。表情は見えないが、彼女の後ろ姿はなんだか寂しそうにも見えた。
「―――出して」
ジーナの声に、は反対しなかった。
フィオは立派な人だと思ったけれど、今の彼女ではマルコと同じ世界を生きることは無理だとは思った。
もう少し大人にならないと。大人になったとしても、マルコの傍にいるのはきっと、もっと大変なのだろうけれど。
「でも、いじわるだね、マルコ」
エンジン音の中で誰にも聞こえないように悪態をついた。
は久しぶりに故郷にもどった。ここはかつてマルコもジーナも居た町で、あの頃とあまり変わっていない。
生家はまだ残っているが、家には誰も住んでおらず、きっと所々傷んでいるだろうと思った。
玄関のドアは戸締まりが完全だったが鍵は勿論持っている。窓ガラスが所々割れているのに目を瞑って掃除すれば、暫く住みつく事が出来そうだ。
「あ……僕の描いたらくがき」
へたくそな飛行艇の絵が壁の隅にあった。絵というよりも、壁に刻んだ傷なのだが。よりによって自室ではなく祖母の目に入るリビングに描いた所為で、大目玉をくらったことを思い出す。
町ではの事を覚えている人もたくさんいた。
小さな頃は人見知りが激しく同年代の友人もいなかったが、軍に入る少し前くらいになると、それなりに話もできるようになっていた。隣家の幼馴染みと結婚をした友人は一晩泊めてくれたし、妹のピアノを直してやったことのある友人は暫く生家に住み着くというと、使っていない衣類を大量に寄越した。
「軍、辞めたんだろ?いままでおつかれさん」
「ありがとう」
「こちらこそ」
前線には出ていないが、戦争に携わっていた者に、町の声はあたたかかった。
稀に軍人を憎む民も居るので良い事ばかりではないのを知っているが、少なくとも故郷で悪い思いをすることはない。
「これからどうするんだ?」
ついでにまたピアノを見てくれ、と言われて見ていると先の事を聞かれる。
「少し……賭けをしてみようかと思って」
「へ?賭け?」
鍵盤を押すと、おかしな音が出て苦笑する。
「いや、そんな大層なものじゃないか……」
「ふーん」
良い直したことで意味が曖昧となり、友人は興味を失ったらしい。
会っていない期間が長く、話したい事や聞きたい事が多くあったから、些細な事など気にされなかった。
故郷に帰って来てひと月程が経つ。
祖母の墓参りに行く事が日課になっていた為、朝早くに家をでるようになった。道中の花屋で働いている友人の妹は、ピアノのお礼にと毎朝売り物にはならない花を分けてくれた。
彼女は再会して一番に、いつまでいるのかと問い、ひと月後には結婚式を挙げるから是非参加してくれと笑った。その幸せそうな笑顔を見ているだけで、自分も幸せな気分になれたので是非参加したいと思っていた。たとえ迎えが来てしまっても、参加しようと。
結局難なくその日を迎える事になり、は久しぶりに正装をした。
花嫁と花婿の後ろ姿を眺め、自分の事ではないのに胸が温まる。やがて教会の外でパーティーが始まり、独身の友人も既婚の友人も酒が入り陽気になって来た所ではその場を辞した。
結婚式を覗きに来ていた近所の子供達が、軍人が居たと言うのだ。
向かうのは、実家のある方。
迷いはなく、走り出す。
家まで、こんなに大急ぎで走って帰ったのは、子供の頃マルコに会いに行こうとしていた時ぶりだ。
荒い息と足音を隠す余裕もなく、家が見える所までやってくる。丁度、家の前に人影を見つけて足を止めた。その音に振り向いた人は、確かに軍の制服を着ていた。走っている間、マルコの飛行艇を作った咎が及んだか、出兵の指示が来たか、脳裏に一瞬よぎったのだがそれは杞憂に終わる。
「フェラーリンさん」
大きな安堵の息と、笑みをこぼしながら呼びかけた。
と口が動くの見ながら、彼に駆け寄る。そして、手を取って家とは違う方へ連れ出した。
「お、おい、どこへ……」
「ここ、僕の町だから」
「ああ」
躊躇いながらもついて来る彼は、の言葉にぎこちなく頷く。意味が分かっているような、分かっていないような様子だ。
「見て」
「海か……」
「ここから見る景色が僕にとっての海」
「綺麗だな」
浜辺から少し離れた所には草原が広がっていて、よくそこでジーナと共にマルコ達を待った。
「いつもここから、海と空を見ていた」
「そうか」
言いながらは歩く。靴と靴下を脱ぐと、後ろで戸惑う声がしたがそれも気にせず波打ち際に足をおろす。
「もう冷たいや」
「服が濡れるぞ。今日は、どうしてそんな格好を?」
「結婚式だった」
素足になったくせに裾を気に留めないに苦笑していたフェラーリンは、一瞬で表情を強ばらせた。
「僕んじゃないよ」
「そうか、良かった」
彼の目に見えた安堵に、思わず口元が緩む。
「ねえ、僕元気そうでしょ」
「ああ」
西日と自分を眩しそうに見るフェラーリンは笑いながら頷いた。
は認めてもらえたことに、柔らかく笑う。その間にフェラーリンも裸足になって海水のある所までやって来た。
「じゃあもう、僕は大丈夫なんだ」
「」
「はい」
目の前に居るフェラーリンを見る。さっきまで笑っていたのに急に言いづらそうな事を秘めた顔をしていて、今度はの身体が強ばった。
フェラーリンは口をはくはくと開閉させ、言葉を紡ごうとしている。真摯な眼差しと、震える唇が酷くアンバランスだ。不安そうな、子供みたいな顔をしていると思った。
「―――、会いたかった……!」
「うん、僕も」
絞り出すような声に対して、へらりと笑ったは乱暴に抱きしめられた。肩で、フェラーリンが恨めしそうな声を上げる。
「逃げていたくせにか」
「大丈夫になろうと思って、僕」
「俺がいなくても?」
「そうだよ、だから僕を追い出したんじゃないの?」
痛い所を突いた所為か腕の力が弱まり、はそこから抜け出した。
少しだけ深い所に行って、膝の上まで海水に浸かる。冷たさに眉をしかめたが、すぐにそれも馴染む。
手を浸し、海水を投げると自分にもフェラーリンにも降り注ぐ。
こうやって、笑いながら意味のない行動もできるようになったのだ、は。
「あはは、しょっぱい」
唇を舐めると、フェラーリンは困ったように笑う。
「本当に俺が居なくても平気か?」
「……うん」
フェラーリンは傷ついたような顔をしているように見えた。
あのときは自分が傷つけられているばかりだと思っていた。苦しい思いをしたのは自分ばかりだと。今でも当時の彼の様子を正確には思い出せないが、マルコとフィオを重ねて考えるとなんとなくわかる。加えて、ここ数年自分に会おうとしてくれていた彼から逃げていた事も自覚している。
「平気―――っていおうと思ってた」
「は?」
海水の中で足を動かして遊ぶを、フェラーリンはあっけにとられたような顔で見た。
「会わない間、寂しいとは思わなかったんだ。あなたのことは忘れてなかった。顔も、温もりも」
濡れた手を組んで肘を掴む。
海の音は心を落ち着かせてくれるが、の心臓は落ち着かなかった。
「会いたかったんだよ、僕も、ずっと」
「ああ……」
「これでも強くなったんだ、元気そうでしょ?心配しなくていいから、だからっ…そばに」
大人になろうとした。大人になったと言われた。大人になったつもりでいた。
けれど、今は子供みたいに泣いていた。
前に泣いたときの方が、まだ我慢ができていた。
静かで、綺麗に泣けた気がした。人から言わせれば、あれは覇気がなかっただけなのだが。
「だめかなあ……?僕」
「」
肘で大粒の涙を拭う。
感情と涙が押し寄せて止まらないは耳鳴りがしていて、フェラーリンが大股で海水の中を歩いて近づいて来た事にも気づかなかった。けれどまた抱きしめられたことも、耳元に唇を寄せて吐息と一緒に名前を呼ばれたこともわかった。
背中を両掌で撫でられても、涙は止まらない。
「……我慢なんてしなくていい」
「うん」
「俺の傍にいてくれ」
耳鳴りが止んだ瞬間に、一番聞きたかった言葉が鼓膜を震わせた。それから海の音と風の音と、教会の鐘の音がした。
―――今日見た花嫁のように幸せになれる。
緩んだ腕の中で促されて顔を上げると、ぼやけた視界でも分かる程間近に彼の顔がある。
「しょっぱいよ、多分」
「構わない」
言い訳を制して塞がれた唇はやはり海の味がして、笑いがこみ上げてきた。
家に甘いチョコレートがあるから帰ろう、と誘うのはいつがいいのか考える。ところがやがて、海水の味は消え、子供のような我儘も消えてしまった。
ただ熱と呼吸を分け合い、幸福を味わうことだけに夢中になっていた。
おわり。
「まだかな、ジーナ」
「それが、お部屋に入ったっきりなんですよ」
風よけのフロントガラスに手をついて、嘆息した。
フィオの行く末が気になる事もあるが、カーチスとの戦いは純粋に見たかったのだ。
「おまたせ、急いで出して!」
「言われなくても!」
ジーナが駆け寄って来て、飛行艇に飛び乗った瞬間に発進させる。ぺろりと唇を舐めて上昇させるまでに、彼女が座ったことを確認するのも怠らない。
「イタリア空軍が出動するそうよ」
「フェラーリンさんから?」
「ええ、だから急いで」
「Si」
緊急性を理解し、は短く返事をして運転を始めた。
「もっと急げないの?」
「これでも一番早いんだって」
途中そんなやりとりをしながらも、まだ空軍の姿が見えないうちにリターンマッチが行われている孤島についた。
飛んでいる姿が見えない事で何故かと首をかしげたが、どうやらただの殴り合いに発展していたらしい。
人が沈んでいるであろう所の海面には白い気泡が浮かぶ。
はそんなものはお構いなしに着水した。このままだとマルコとカーチスの上に乗るが、そうなったらカウントをとっている男が引っ張り出せば良いだけの話だ。
「マルコ、マルコ聞いてる?」
飛行艇はなんとか、手前で停まる。否、停めてもらった。
「あなたもう一人女の子を不幸にする気なの?」
その口ぶりだとジーナが不幸なように聞こえる。
マルコが日差しのもとへ出て会いに来てくれるのを待っているのだから、そうではない今、幸せとは言い難い、という意味なのか。
喪失について共に悲しみに暮れて来たけれど、気丈に振る舞っていた彼女から出て来た、些細な本音にもどかしさを感じずにはいられない。自分が幸せにすることはできないのだが。
大量の泡を吐いたマルコが起き上がるのを待ち、カウントはナインのところで勿体ぶって止まった。
「ポルコ!!!!」
マルコが立ち上がると歓声がわいた。その中に可愛らしい声が混じる。
とジーナは安堵しながら、マルコとフィオが抱き合っているのを眺めた。やがてジーナはあたりの気を引き締めるように手を叩き、イタリア空軍がここに向かっていることをつげた。
後ろ暗い者達ばかりなので、クモの子を散らす様にそれぞれ逃げて行く。その様子は少し面白いとさえ思った。
も一応、捕まっては困るので早く帰りたい気持ちで一杯だ。
たとえ、彼がくるかもしれなくとも、ここでは会えない。
「お前はジーナの艇にのるんだ……!」
「いやよ!や!ポルコの艇にのる!パートナーだって言ったじゃない!」
「ジーナ、こいつをカタギの世界に戻してやってくれ」
「……ずるい人。いつもそうするのね」
「すまねえ、行ってくれ」
前の自分と似た境遇を感じながら、機体の中落とされたフィオを見る。表情は見えないが、彼女の後ろ姿はなんだか寂しそうにも見えた。
「―――出して」
ジーナの声に、は反対しなかった。
フィオは立派な人だと思ったけれど、今の彼女ではマルコと同じ世界を生きることは無理だとは思った。
もう少し大人にならないと。大人になったとしても、マルコの傍にいるのはきっと、もっと大変なのだろうけれど。
「でも、いじわるだね、マルコ」
エンジン音の中で誰にも聞こえないように悪態をついた。
は久しぶりに故郷にもどった。ここはかつてマルコもジーナも居た町で、あの頃とあまり変わっていない。
生家はまだ残っているが、家には誰も住んでおらず、きっと所々傷んでいるだろうと思った。
玄関のドアは戸締まりが完全だったが鍵は勿論持っている。窓ガラスが所々割れているのに目を瞑って掃除すれば、暫く住みつく事が出来そうだ。
「あ……僕の描いたらくがき」
へたくそな飛行艇の絵が壁の隅にあった。絵というよりも、壁に刻んだ傷なのだが。よりによって自室ではなく祖母の目に入るリビングに描いた所為で、大目玉をくらったことを思い出す。
町ではの事を覚えている人もたくさんいた。
小さな頃は人見知りが激しく同年代の友人もいなかったが、軍に入る少し前くらいになると、それなりに話もできるようになっていた。隣家の幼馴染みと結婚をした友人は一晩泊めてくれたし、妹のピアノを直してやったことのある友人は暫く生家に住み着くというと、使っていない衣類を大量に寄越した。
「軍、辞めたんだろ?いままでおつかれさん」
「ありがとう」
「こちらこそ」
前線には出ていないが、戦争に携わっていた者に、町の声はあたたかかった。
稀に軍人を憎む民も居るので良い事ばかりではないのを知っているが、少なくとも故郷で悪い思いをすることはない。
「これからどうするんだ?」
ついでにまたピアノを見てくれ、と言われて見ていると先の事を聞かれる。
「少し……賭けをしてみようかと思って」
「へ?賭け?」
鍵盤を押すと、おかしな音が出て苦笑する。
「いや、そんな大層なものじゃないか……」
「ふーん」
良い直したことで意味が曖昧となり、友人は興味を失ったらしい。
会っていない期間が長く、話したい事や聞きたい事が多くあったから、些細な事など気にされなかった。
故郷に帰って来てひと月程が経つ。
祖母の墓参りに行く事が日課になっていた為、朝早くに家をでるようになった。道中の花屋で働いている友人の妹は、ピアノのお礼にと毎朝売り物にはならない花を分けてくれた。
彼女は再会して一番に、いつまでいるのかと問い、ひと月後には結婚式を挙げるから是非参加してくれと笑った。その幸せそうな笑顔を見ているだけで、自分も幸せな気分になれたので是非参加したいと思っていた。たとえ迎えが来てしまっても、参加しようと。
結局難なくその日を迎える事になり、は久しぶりに正装をした。
花嫁と花婿の後ろ姿を眺め、自分の事ではないのに胸が温まる。やがて教会の外でパーティーが始まり、独身の友人も既婚の友人も酒が入り陽気になって来た所ではその場を辞した。
結婚式を覗きに来ていた近所の子供達が、軍人が居たと言うのだ。
向かうのは、実家のある方。
迷いはなく、走り出す。
家まで、こんなに大急ぎで走って帰ったのは、子供の頃マルコに会いに行こうとしていた時ぶりだ。
荒い息と足音を隠す余裕もなく、家が見える所までやってくる。丁度、家の前に人影を見つけて足を止めた。その音に振り向いた人は、確かに軍の制服を着ていた。走っている間、マルコの飛行艇を作った咎が及んだか、出兵の指示が来たか、脳裏に一瞬よぎったのだがそれは杞憂に終わる。
「フェラーリンさん」
大きな安堵の息と、笑みをこぼしながら呼びかけた。
と口が動くの見ながら、彼に駆け寄る。そして、手を取って家とは違う方へ連れ出した。
「お、おい、どこへ……」
「ここ、僕の町だから」
「ああ」
躊躇いながらもついて来る彼は、の言葉にぎこちなく頷く。意味が分かっているような、分かっていないような様子だ。
「見て」
「海か……」
「ここから見る景色が僕にとっての海」
「綺麗だな」
浜辺から少し離れた所には草原が広がっていて、よくそこでジーナと共にマルコ達を待った。
「いつもここから、海と空を見ていた」
「そうか」
言いながらは歩く。靴と靴下を脱ぐと、後ろで戸惑う声がしたがそれも気にせず波打ち際に足をおろす。
「もう冷たいや」
「服が濡れるぞ。今日は、どうしてそんな格好を?」
「結婚式だった」
素足になったくせに裾を気に留めないに苦笑していたフェラーリンは、一瞬で表情を強ばらせた。
「僕んじゃないよ」
「そうか、良かった」
彼の目に見えた安堵に、思わず口元が緩む。
「ねえ、僕元気そうでしょ」
「ああ」
西日と自分を眩しそうに見るフェラーリンは笑いながら頷いた。
は認めてもらえたことに、柔らかく笑う。その間にフェラーリンも裸足になって海水のある所までやって来た。
「じゃあもう、僕は大丈夫なんだ」
「」
「はい」
目の前に居るフェラーリンを見る。さっきまで笑っていたのに急に言いづらそうな事を秘めた顔をしていて、今度はの身体が強ばった。
フェラーリンは口をはくはくと開閉させ、言葉を紡ごうとしている。真摯な眼差しと、震える唇が酷くアンバランスだ。不安そうな、子供みたいな顔をしていると思った。
「―――、会いたかった……!」
「うん、僕も」
絞り出すような声に対して、へらりと笑ったは乱暴に抱きしめられた。肩で、フェラーリンが恨めしそうな声を上げる。
「逃げていたくせにか」
「大丈夫になろうと思って、僕」
「俺がいなくても?」
「そうだよ、だから僕を追い出したんじゃないの?」
痛い所を突いた所為か腕の力が弱まり、はそこから抜け出した。
少しだけ深い所に行って、膝の上まで海水に浸かる。冷たさに眉をしかめたが、すぐにそれも馴染む。
手を浸し、海水を投げると自分にもフェラーリンにも降り注ぐ。
こうやって、笑いながら意味のない行動もできるようになったのだ、は。
「あはは、しょっぱい」
唇を舐めると、フェラーリンは困ったように笑う。
「本当に俺が居なくても平気か?」
「……うん」
フェラーリンは傷ついたような顔をしているように見えた。
あのときは自分が傷つけられているばかりだと思っていた。苦しい思いをしたのは自分ばかりだと。今でも当時の彼の様子を正確には思い出せないが、マルコとフィオを重ねて考えるとなんとなくわかる。加えて、ここ数年自分に会おうとしてくれていた彼から逃げていた事も自覚している。
「平気―――っていおうと思ってた」
「は?」
海水の中で足を動かして遊ぶを、フェラーリンはあっけにとられたような顔で見た。
「会わない間、寂しいとは思わなかったんだ。あなたのことは忘れてなかった。顔も、温もりも」
濡れた手を組んで肘を掴む。
海の音は心を落ち着かせてくれるが、の心臓は落ち着かなかった。
「会いたかったんだよ、僕も、ずっと」
「ああ……」
「これでも強くなったんだ、元気そうでしょ?心配しなくていいから、だからっ…そばに」
大人になろうとした。大人になったと言われた。大人になったつもりでいた。
けれど、今は子供みたいに泣いていた。
前に泣いたときの方が、まだ我慢ができていた。
静かで、綺麗に泣けた気がした。人から言わせれば、あれは覇気がなかっただけなのだが。
「だめかなあ……?僕」
「」
肘で大粒の涙を拭う。
感情と涙が押し寄せて止まらないは耳鳴りがしていて、フェラーリンが大股で海水の中を歩いて近づいて来た事にも気づかなかった。けれどまた抱きしめられたことも、耳元に唇を寄せて吐息と一緒に名前を呼ばれたこともわかった。
背中を両掌で撫でられても、涙は止まらない。
「……我慢なんてしなくていい」
「うん」
「俺の傍にいてくれ」
耳鳴りが止んだ瞬間に、一番聞きたかった言葉が鼓膜を震わせた。それから海の音と風の音と、教会の鐘の音がした。
―――今日見た花嫁のように幸せになれる。
緩んだ腕の中で促されて顔を上げると、ぼやけた視界でも分かる程間近に彼の顔がある。
「しょっぱいよ、多分」
「構わない」
言い訳を制して塞がれた唇はやはり海の味がして、笑いがこみ上げてきた。
家に甘いチョコレートがあるから帰ろう、と誘うのはいつがいいのか考える。ところがやがて、海水の味は消え、子供のような我儘も消えてしまった。
ただ熱と呼吸を分け合い、幸福を味わうことだけに夢中になっていた。
おわり。
2016/12/3
![]()
![]()
![]()
Title
by
yaku 30
no uso